2018年6月30日(土)
水分補給について
健康×56

今日は帯広も気温が上がっていますね。
来週の月曜日までは30度近くまで上がる日が続くようです。
北海道もこれから夏本番という時期に入りますが、真夏の体調管理はとても大切です。
特に、屋外での仕事が多い方やスポーツで汗をたくさんかく方、ご高齢の方については、正しい知識を知り、実践していくことが必要になります。
まず、夏の基本的な対策として「水分をこまめに摂るように」とよく言われますが、実はこれが大きな誤解を生んでいるケースがあります。
たしかに、夏場は汗をたくさんかきますから、水分をいつも以上に摂取することが望ましいです。
ただ、ここでいう水分とは、お茶や清涼飲料水ではなく、純粋な「水」のことを指します。
お茶やコーヒーには利尿作用があるため、多量に飲むと身体の水分が排出されすぎてしまい、脱水症状を招く可能性があります。
そして、清涼飲料水やスポーツドリンク、コーラ等の飲み物はさらに良くない影響を及ぼします。
スポーツドリンクには500mlあたり20~34gの砂糖(角砂糖 5~8個分)、コーラ等の炭酸飲料には500mlあたり40~65gの砂糖(角砂糖 10~16個分)が含まれています。
大量の糖分を含むこれらの飲み物には、急性の糖尿病を引き起こすリスクがあるのです。
※以下、ウィキペディアより抜粋
「ペットボトル症候群(ペットボトルしょうこうぐん、英語: PET bottle syndrome)とは、スポーツドリンク、清涼飲料水などを大量に飲み続けることによっておこる急性の糖尿病である。正式名称はソフトドリンク(清涼飲料水)・ケトアシドーシス。清涼飲料水ケトーシスとも呼ぶこともある。ソフトドリンクやスポーツドリンクの急激な大量摂取だけでなく、みかんの缶詰やアイスクリームなどの糖分の多い食品の大量摂食でも発症することが報告されている。」
汗をたくさんかいた後に、スポーツドリンクをがぶ飲みしたり、アイスクリームを食べ過ぎたりすると、血糖値のコントロールができなくなり、身体はさらに疲弊してしまいます。
暑いときは、純粋な「水」をしっかり飲むように心がけていきたいですね。
ちなみに、当院では施術のあとも水分をたくさん摂るようにお伝えしています。
施術によって身体の老廃物を排出する反応が起こるのですが、そのときに水が媒介役となってくれるためです。
水は、身体のデトックスを促す役割をしてくれるんですね。
それでは、暑さに負けず、今日も元気に過ごしていきましょう(^^)
来週の月曜日までは30度近くまで上がる日が続くようです。
北海道もこれから夏本番という時期に入りますが、真夏の体調管理はとても大切です。
特に、屋外での仕事が多い方やスポーツで汗をたくさんかく方、ご高齢の方については、正しい知識を知り、実践していくことが必要になります。
まず、夏の基本的な対策として「水分をこまめに摂るように」とよく言われますが、実はこれが大きな誤解を生んでいるケースがあります。
たしかに、夏場は汗をたくさんかきますから、水分をいつも以上に摂取することが望ましいです。
ただ、ここでいう水分とは、お茶や清涼飲料水ではなく、純粋な「水」のことを指します。
お茶やコーヒーには利尿作用があるため、多量に飲むと身体の水分が排出されすぎてしまい、脱水症状を招く可能性があります。
そして、清涼飲料水やスポーツドリンク、コーラ等の飲み物はさらに良くない影響を及ぼします。
スポーツドリンクには500mlあたり20~34gの砂糖(角砂糖 5~8個分)、コーラ等の炭酸飲料には500mlあたり40~65gの砂糖(角砂糖 10~16個分)が含まれています。
大量の糖分を含むこれらの飲み物には、急性の糖尿病を引き起こすリスクがあるのです。
※以下、ウィキペディアより抜粋
「ペットボトル症候群(ペットボトルしょうこうぐん、英語: PET bottle syndrome)とは、スポーツドリンク、清涼飲料水などを大量に飲み続けることによっておこる急性の糖尿病である。正式名称はソフトドリンク(清涼飲料水)・ケトアシドーシス。清涼飲料水ケトーシスとも呼ぶこともある。ソフトドリンクやスポーツドリンクの急激な大量摂取だけでなく、みかんの缶詰やアイスクリームなどの糖分の多い食品の大量摂食でも発症することが報告されている。」
汗をたくさんかいた後に、スポーツドリンクをがぶ飲みしたり、アイスクリームを食べ過ぎたりすると、血糖値のコントロールができなくなり、身体はさらに疲弊してしまいます。
暑いときは、純粋な「水」をしっかり飲むように心がけていきたいですね。
ちなみに、当院では施術のあとも水分をたくさん摂るようにお伝えしています。
施術によって身体の老廃物を排出する反応が起こるのですが、そのときに水が媒介役となってくれるためです。
水は、身体のデトックスを促す役割をしてくれるんですね。
それでは、暑さに負けず、今日も元気に過ごしていきましょう(^^)
2018年6月27日(水)
急性痛と慢性痛
オステオパシー×40
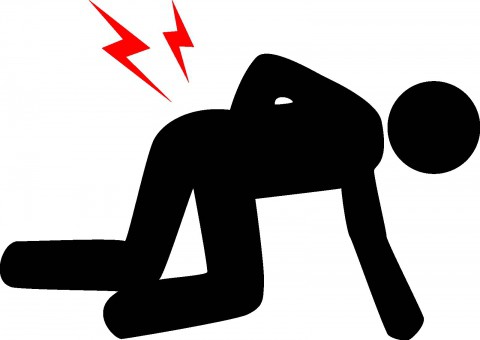
痛みには様々な種類がありますが、「発症から経過した時間」で分けるとすると、「急性痛」と「慢性痛」の2つに大別されます。
ぎっくり腰やスポーツによるケガなど、突然現れる痛みが急性痛、
何か月にも渡って持続する痛みが慢性痛です。
急性痛は、その衝撃の程度にもよりますが、比較的早い段階で治癒に向かいます。
一方、慢性痛になると、その間に筋膜や靭帯の質的変化が進んでしまうため、それらの組織を元の状態に戻すにはそれなりの時間を要します。
さらに、慢性痛は病院で検査しても「異常なし」と言われることが多いため、薬や湿布で対症療法的に様子をみるしかない、と思われがちです。
当院にも、十年来の痛みを抱える方々がいらっしゃいますが、やはり急性痛の場合よりも時間が必要となりますし、経過が長ければ長いほど元の状態に戻すのは難しくなります。
大事なことは、「急性痛のときにしっかり対処すること」です。
急性痛の際に適切な処置を施さないまま放置すると、慢性痛に移行してしまったり、数年後に別の症状を引き起こす要因にもなります。
RICE処置(R:Rest安静、I:Iceアイシング、C:Compression圧迫、E:Elevation拳上)も良いですが、そのあとに衝撃を受けた組織をできるだけ元の状態に戻しておくことが、慢性痛予防のためにも大切だと思います。
ぎっくり腰やスポーツによるケガなど、突然現れる痛みが急性痛、
何か月にも渡って持続する痛みが慢性痛です。
急性痛は、その衝撃の程度にもよりますが、比較的早い段階で治癒に向かいます。
一方、慢性痛になると、その間に筋膜や靭帯の質的変化が進んでしまうため、それらの組織を元の状態に戻すにはそれなりの時間を要します。
さらに、慢性痛は病院で検査しても「異常なし」と言われることが多いため、薬や湿布で対症療法的に様子をみるしかない、と思われがちです。
当院にも、十年来の痛みを抱える方々がいらっしゃいますが、やはり急性痛の場合よりも時間が必要となりますし、経過が長ければ長いほど元の状態に戻すのは難しくなります。
大事なことは、「急性痛のときにしっかり対処すること」です。
急性痛の際に適切な処置を施さないまま放置すると、慢性痛に移行してしまったり、数年後に別の症状を引き起こす要因にもなります。
RICE処置(R:Rest安静、I:Iceアイシング、C:Compression圧迫、E:Elevation拳上)も良いですが、そのあとに衝撃を受けた組織をできるだけ元の状態に戻しておくことが、慢性痛予防のためにも大切だと思います。
2018年6月14日(木)
痛みを招く要因
健康×56
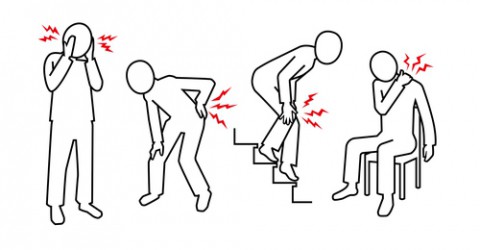
痛みを左右する要因は、身体の内外に存在します。
・ホルモン動態
女性は、閉経前から閉経期にかけて痛みを感じやすくなる
・代謝
消化不良が関節痛を引き起こすことがある
・遺伝
リウマチなど、家系的体質からくるものもある
・心理的要因
長期間に渡ってストレスや緊張を感じると、血流が悪くなり痛みを感じやすくなる
・機械的要因
関節に対して強い衝撃や負荷が加わると、痛みは増強する
・気候
気温が低かったり、湿度が高いと、関節の痛みは増強する
・気圧
急に高度の高いところへ行くと、痛みが生じることがある
この中で、自分でコントロールできること、できないことを識別するということが大切です。
例えば、代謝を改善するために食生活を改めたり、ストレスを軽減するために自分なりのストレス解消法を探ることはできますが、遺伝的な要因や気候、女性の閉経などについては避けることはできません。
前者の「コントロールできること」に対して意識的に変えていくことが、痛みを緩和し、健康を取り戻すためのステップとなります。
・ホルモン動態
女性は、閉経前から閉経期にかけて痛みを感じやすくなる
・代謝
消化不良が関節痛を引き起こすことがある
・遺伝
リウマチなど、家系的体質からくるものもある
・心理的要因
長期間に渡ってストレスや緊張を感じると、血流が悪くなり痛みを感じやすくなる
・機械的要因
関節に対して強い衝撃や負荷が加わると、痛みは増強する
・気候
気温が低かったり、湿度が高いと、関節の痛みは増強する
・気圧
急に高度の高いところへ行くと、痛みが生じることがある
この中で、自分でコントロールできること、できないことを識別するということが大切です。
例えば、代謝を改善するために食生活を改めたり、ストレスを軽減するために自分なりのストレス解消法を探ることはできますが、遺伝的な要因や気候、女性の閉経などについては避けることはできません。
前者の「コントロールできること」に対して意識的に変えていくことが、痛みを緩和し、健康を取り戻すためのステップとなります。
2018年6月4日(月)
過去の既往歴と現在の症状
健康×56

初診の患者さんが来院された際は、まず最初に問診をします。
現在の症状に関すること(部位や痛みの程度、いつから生じているのか等)はもちろん大切な情報ですが、それと同じぐらい聞いておきたいのが「既往歴」です。
病院の問診票でも「既往歴」の欄があると思いますが、過去にどんな病気・ケガをしているのかという情報は、身体を評価する上でとても重要です。
というのも、オステオパシー的視点からいうと、身体は過去の病気やケガを記憶しているからです。
どういうことかというと、例えば過去に追突されてムチウチにあったとします。
ムチウチは、外傷の中でもかなり大きな衝撃が身体に加わるのですが、その衝撃は全身の筋膜の捩れや硬直を引き起こします。
このとき、筋膜はこの状態(捩れや硬さ)を記憶するといわれています。
つまり、その後自覚的な症状は消え去ったとしても、数年後にその部位をきっかけとして別の症状が現れる可能性があるということです。
実際に、過去の足首の捻挫や盲腸の手術痕が腰痛を引き起こしている、
あるいは、ムチウチが頭痛や肩こりに影響している、
等と思われるケースは多くみられます。
このようなお話を患者さんにすると、「そんなこと関係あるんだ」と驚かれる方が多いのですが、過去の既往と現在の症状には深い関係があるのです。
現在の症状に関すること(部位や痛みの程度、いつから生じているのか等)はもちろん大切な情報ですが、それと同じぐらい聞いておきたいのが「既往歴」です。
病院の問診票でも「既往歴」の欄があると思いますが、過去にどんな病気・ケガをしているのかという情報は、身体を評価する上でとても重要です。
というのも、オステオパシー的視点からいうと、身体は過去の病気やケガを記憶しているからです。
どういうことかというと、例えば過去に追突されてムチウチにあったとします。
ムチウチは、外傷の中でもかなり大きな衝撃が身体に加わるのですが、その衝撃は全身の筋膜の捩れや硬直を引き起こします。
このとき、筋膜はこの状態(捩れや硬さ)を記憶するといわれています。
つまり、その後自覚的な症状は消え去ったとしても、数年後にその部位をきっかけとして別の症状が現れる可能性があるということです。
実際に、過去の足首の捻挫や盲腸の手術痕が腰痛を引き起こしている、
あるいは、ムチウチが頭痛や肩こりに影響している、
等と思われるケースは多くみられます。
このようなお話を患者さんにすると、「そんなこと関係あるんだ」と驚かれる方が多いのですが、過去の既往と現在の症状には深い関係があるのです。
2018年5月31日(木)
6月の休診日
| << | >> |
