2012年1月18日(水)
『ドリームボックス』
どうぶつ「観察日記」_6×202
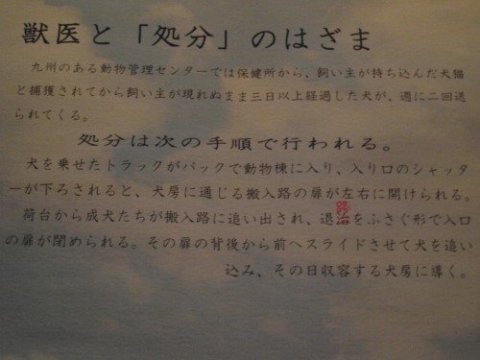
獣医と「処分」のはざま
九州のある動物管理センターでは保健所から、飼い主が持ち込んだ犬猫と捕獲されてから飼い主が現れぬまま三日以上経過した犬が、週に二回送られてくる。
処分は次の手順で行われる。
犬を乗せたトラックがバックで動物棟に入り、入り口のシャッターが下ろされると、犬房に通じる搬入路の扉が左右に開けられる。
荷台から成犬たちが搬入路に追い出され、退路をふさぐ形で入口の扉が閉められる。その扉の背後から前へスライドさせて犬を追い込み、その日収容する犬房に導く。
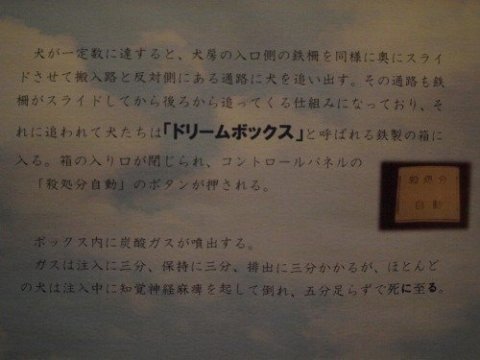
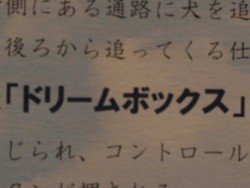
犬が一定数に達すると、犬房の入口側の鉄柵を同様に奥にスライドさせて搬入路と反対側にある通路に犬を追い出す。その通路も鉄柵がスライドしてから後ろから追ってくる仕組みになっており、それに追われて犬たちは「ドリームボックス」と呼ばれる鉄製の箱に入る。箱の入り口が閉じられ、コントロールパネルの
「殺処分自動」のボタンが押される。

ボックス内に炭酸ガスが噴出する。
ガスは注入に三分、保持に三分、排出に三分かかるが、ほとんどの犬は注入中に知覚神経麻痺を起して倒れ、五分足らずで死に至る。
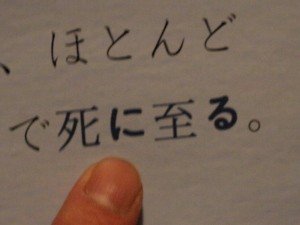
これが最も苦痛を与えない方法とされ、全国の類似施設のほとんどがこの方法で処分を行っている。
一方麻袋に入れられて保健所から送られてくる猫や子犬たちは、トラックから小型処分器に入れられ、成犬以上に高濃度の炭酸ガスが注入される。生まれて間もない子犬や猫は呼吸量が少ないため、それでも死ぬまでの時間は成犬よりも長くかかるという。

こうして処分犬猫は二基ある焼却炉へと移され、
約五時間の焼却時間が終って炉の扉が開けられる
時には、カラカラの白い骨灰となっている。
このセンターで働く十人の職員のうち、四人は獣医師の資格を持つ。
K所長もその一人だ。獣医が動物を処分する施設にいることに違和感を覚える人もいるかもしれないが、彼らが仕事を通じて貢献するのは、動物の福利ではなく、人間の福利であり、診療相手が家畜からペットになっても、それが変わるわけではない。本来、犬猫の処分と獣医の仕事とは、何ら矛盾するものではない
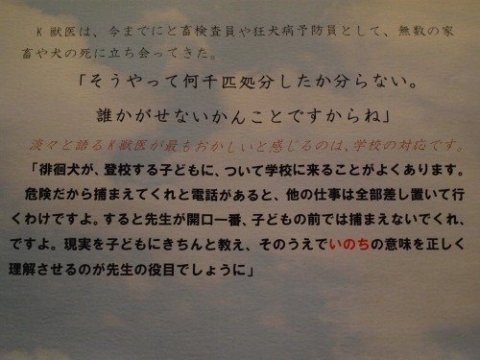
K獣医は、今までにと畜検査員や狂犬病予防員として、無数の家畜や犬の死に立ち会ってきた。
「そうやって何千匹処分したか分らない。
誰かがせないかんことですからね」
淡々と語るK獣医が最もおかしいと感じるのは、学校の対応です。
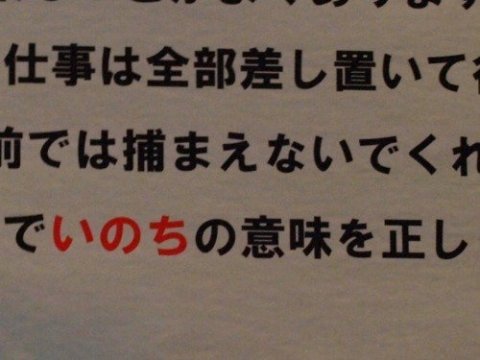
危険だから捕まえてくれと電話があると、他の仕事は全部差し置いて行くわけですよ。すると先生が開口一番、子どもの前では捕まえんでくれ、ですよ。現実を子どもにきちんと教え、そのうえでいのちの意味を正しく理解させるのが先生の役目でしょうに」
現実に目をふさぎ、表面だけ優しげに取り繕って語られる「いのちを大切に」という言葉。そんなものが子どもたちの胸に響くはずがない。それどころか、その態度から子どもたちは建前と本音を使い分ける今の社会のずるさを学ぶだろう。
それが、こうした業務に携わる人たちへの偏見をはぐくみ、逆にいのちを軽んずる風潮を生んでいることに、気づいている人は少ない。
| コメント |
このブログはコメントを受け付けていません
